

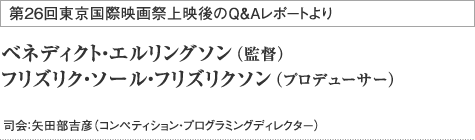
監督:私の監督デビュー作でありますし、映画祭に公式に選ばれたのも初めてですので感謝したいと思います。アイデアがどこから来たかということですが、動物の中から見た人間、人間の中の動物の部分を描きたいなと思いました。
人間を動物に例える時というのは冷酷さだったり、残虐性だったりネガティブなことを表す場合が多いと思うのですが、でも動物というのは愛すべきものでもあるわけで、人間の中の動物にはいい面もあるのではないかと思いました。楽しい映画、見ていい気持ちになる映画を作ったつもりです。もちろん、後味はありますけれども。
監督:まず言いたいのは、クレジット上に出てくる「ここに出てくる動物たちは全く傷つけられていません」というのは本当だということです。ウエスタン映画が盛んな頃に、たくさんの馬が殺されたハリウッドではありませんので。ハリウッドも今は違うかもしれませんが、この映画に限っては違います。私たちはみんな馬が好きでしたし、馬がどういう行動をするのかというのも大体わかっているので。残虐にみえるシーンも「ムーヴィー・マジック」、つまり映画の魔法あるいはもともと自然の営みだということです。私も撮影監督も馬が大好きな「ホースマン」なので、ああいう映画が撮れたということは本当に幸運でした。大抵のテイクはワンテイクしか撮れず、チャンスも一度しかなかったんです。交尾のシーンや海の中を泳いでいくシーンは、あの瞬間しかチャンスがなかったのでワンテイクで撮ったのです。天候にも助けられ、なにか精霊のようなものが助けてくれたのかもしれませんね。画面を一つ一つ分析していくと可能だということがおわかりになると思うのですが、90%が実写で、デジタル・エフェクトを使っているのは1~2シーンくらいしかありません。

フリズリク・ソール・フリズリクソン:日本にまた来ることができとても嬉しいです。日本の観客の方はとてもオープンマインドな感じがしてとても好きなのですが、その点は(母国の)アイスランドの人々とよく似ているような気がします。これは日本もアイスランドも魚をたくさん食べるからでしょうか(笑)。
監督:馬を演出することは実に簡単なことです。私自身も馬に乗ることが好きなので、馬のことをよく知っているつもりですが、馬の注目を引くときは馬を使えばよいのです。例えばカメラを回している時に、カメラの後ろに友達の馬や敵だと思っている別の馬などそれぞれ違う馬をシーンごとに配置しておけばよかったのです。これが我々の馬を扱う秘訣なので、ぜひ馬の映画を撮る時にはこのテクニックを使ってみてください(笑)。
交尾のシーンは演出で何とか撮るということができませんでした。自然に起こるのを待つしかないため5台のカメラを用意してその時が来るのを待っていたのですが、結果1度しかチャンスはありませんでした。全てはキャスティングとタイミングの問題ということです。
監督:そうですね、私の頭の中にあるファンタジーもありますし、私が小さい頃に働いていた田舎で見聞きしたエピソードもあります。この映画は私にとってセラピーみたいなものでした。私はレイキャビック(アイスランドの首都)出身の都会っ子なんですが、幼い頃4年くらいに亘って夏に田舎で、この映画で描かれているような馬がいるコミュニティで働いたことがあり、その際すごくカルチャーショックを感じました。この映画を作ることによって、そのカルチャーショックを癒すことができました。

監督:ここに出てくる役者さんたちは全員私の友達、あるいは舞台仲間なんです。特に一人とは毎日、寝食を共にしている、つまり私の妻なんですが、それ以外にも毎日会っている舞台仲間がいたりして、本当に家族のような人たちです。
皆すごく馬が大好きで、馬に乗るのも上手な人で、アイスランドにおいては馬に乗る、馬を所有するというのは別に金持ちとか貴族の趣味ではなくて、皆がやることなんです。お金もそんなにかからないし、文化のひとつと言っていいと思います。舞台仲間は特に親しくしている人が多くて、まず私の役者を選ぶ基準は馬に乗れることで、馬によく乗れる人たちというのがたまたまいい役者であったということです。
監督:馬の目を撮るのに何が一番大変だったかというと、馬が動かないようにさせることでした。これは私たちが見つけたトリックなんですが、馬の足を一本上げるんです。3本足で立たせると馬が動かなくなると。これも皆さん、馬の映画を撮るときにはぜひ使ってください(笑)。
馬の瞳はいろんなエピソードにリズムをつけるためにとても大切でした。また、馬の魂に入っていく方法の1つでもありました。舞台ではよく、「観客の目となり、歯となる」という言い方をするんですが、つまりコンタクトをとる、絆を作るということなんです。その瞳を映すことで、それがコンタクトになるという意味を込めています。
監督:黒澤監督にも非常に影響を受けたのですが、小津(安二郎)監督にも影響を受けました。馬と人を撮るためにはフレームが低くないといけないんですね。中心がすごく低くなくてはいけないということで、私たちはそのアングルを「オズ」と呼んでいました(笑)。撮影現場で「オズ、オズ」と言っていたのは、それはアングルを低くしなさいという意味でした。
この映画は犯罪が出てくるわけでもなく庶民とコミュニティの話なんですが、いろんなアクシデントが起こるところはちょっと黒澤っぽいかもしれません。脚本を書く時にアメリカでは人を説得しなくてはいけないというようなことを言いますが、私としてはこの脚本の形、形式はパゾリーニとか黒澤の『羅生門』といったものに近いのかなと思います。あまりクリシェ(型にはまった)ではない形になっていると思います。
